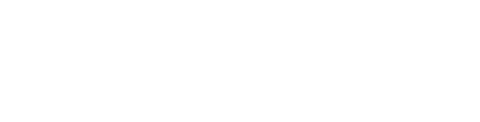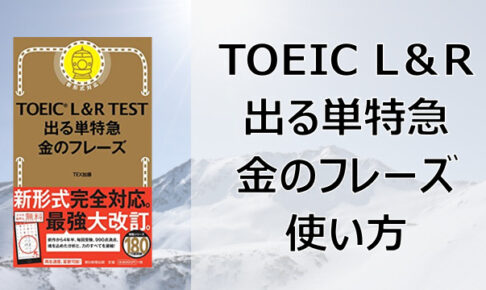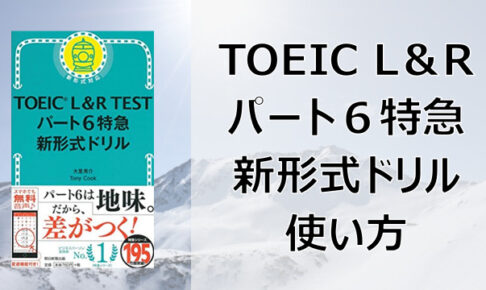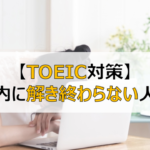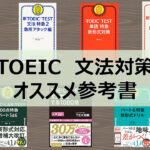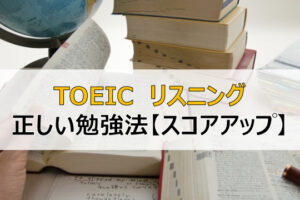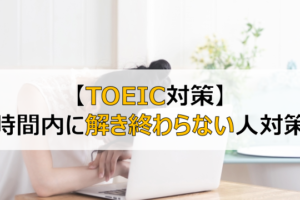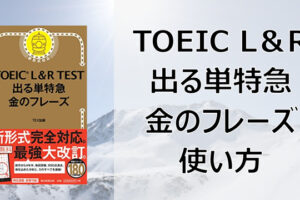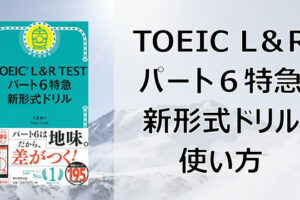こんにちは。ゆうや(@yuya596)です。
本日はTEX加藤先生執筆の「TOEIC L&Rテスト 文法問題 でる1000問」の効果や使い方、デメリットなどを徹底解説します。
TEX加藤先生は金フレや金センの執筆で有名であり、参考書の信頼度も抜群です。

ただし、でる1000は金フレと違って全員に無条件でオススメ出来るわけではありません。
買うべきかどうかも含めて、この記事を参考に検討ください!
Contents
「でる1000」を使うメリット
でる1000を使うメリットは、文法問題を高速かつ正確に解けるようになることです。
そもそもTOEICでハイスコアを獲得するためには、文法問題を高速に処理して、読解問題に時間を残すことが大切です。
でる1000はPart5の問題を1000題以上練習できるため、最後までやりきれば問題処理能力が身につきます。
当然ですが、処理速度だけでなく正答率も上がりますし、単語や語彙力も増強されるため、付随してPart7の得点にもつながります。

でる1000の効果的な使い方
続いてでる1000の効果的な使い方を説明します。
「でる1000」は「品詞・動詞…」など出題単元ごとの7つの章(659題)と、13セットの模試(390題)、合計1049題で構成されています。
まずは7つの章を1週します。その際は以下の点を意識して下さい。
- 1題30秒以内に回答
- 間違っても正解でも解説を読む
- 分からない単語をチェックする
- 間違えた問題をチェックする
問題量がかなり多いので大変ですが、1周するのに2~3週間目安で、一気に勉強する方が身につきます。
1週終えたら、間違えた問題のみを再度解きます。
2週目でも間違えた問題は、付箋でマークしたり、紙に書きだすなどして、試験直前に復習できるようにしておきましょう。
出題単元ごとの章は一旦2周でOKです。終わったらそのまま模試を13セット解きましょう。
模試は実際のテストだと思って、時間を測りながら挑戦します。

模試で間違えた問題は、不正解を選んだ理由分析し、自分のミスのパターンを掴んでください。
ここまで使いこなせば、高速かつ正確な問題処理能力が身につきます。文法問題で9割以上の得点を出せるようになっているはずです。
「でる1000」のデメリット
でる1000はスコアアップに直結する非常に優れた参考書ですが、以下のデメリットもあります。
- アウトプットに特化している
- 解説が淡泊
- Part6の対策が出来ない
1つずつ見ていきましょう。
アウトプットに特化している
でる1000は問題を解くことに特化しているため、語彙や基本的な文法知識のインプットとして使うには効率が悪いです。
単語特急や文法特急で必要な知識をインプットした上で、でる1000を使いましょう。
解説が淡泊
でる1000の解説は必要最低限のみであり、ある程度の文法知識を持っていることが前提になっています。
初心者には解説が物足りなく、挫折する可能性が高いです。
Part6対策が出来ない
でる1000は全てPart5形式での問題です。TEX加藤先生いわく、Part6はPart5の知識で解けるため敢えてPart6の形式を作っていないようです。
もしPart6のスコアが思うように上がらなかったら「Part6特急」を勉強することをオススメします。

詳しくは以下の記事で解説しているので、読んでみて下さい。
「でる1000」を使うべき人・使うべきでない人
ここまでの内容から、でる1000を使うべき人・使う必要が無い人はそれぞれ次の通りです。
<使うべき人>
- TOEIC800点以上が目標
- 文法問題の得点が伸び悩んでいる
- 文法問題のアウトプットが足りていない
<使う必要が無い人>
- TOEICの目標が800点未満
- 文法や語彙の知識が少ない
- リスニング対策が終わっていない
もし目標スコアが800点未満であれば、文法特急を急所アタック編まで実施すれば対策は充分です。
また、リスニング対策や、文法・語彙のインプットの方がスコアに大きく直結するので、先にそれらから勉強しましょう。
まとめ
でる1000は問題処理能力を身につけるうってつけの参考書であり、ハイスコアを狙う人には必須参考書です。
一方で800点未満が目標の方は1000題も解く必要はありませんし、でる1000よりも優先して勉強すべき分野もあります。
ボリューミーな参考書であるだけに、何も考えずに取り掛かると時間を無駄にしてしまいます。
自分にとって必要な参考書なのか、しっかり見極めたうえで取り組みましょう!